ブログ

ブログ
肩こり・更年期障害、その原因と対処法|鍼灸の効果を徹底解説!つらい症状を根本改善
2025/08/21
肩こり、そして更年期。年齢を重ねるごとに増していく体の悩み、どうにかしたいですよね。特に肩こりは、更年期障害の代表的な症状の一つ。放置すると日常生活にも支障をきたす深刻な問題になりかねません。
つらい肩こりと更年期、その関係性を知り、適切な対処法を見つけることが、快適な生活への第一歩です。この記事では、肩こりと更年期障害の密接な関係、それぞれの原因、そして効果的な対処法を詳しく解説します。さらに、近年注目されている鍼灸療法が、肩こりや更年期障害にどのように効果を発揮するのか、そのメカニズムにも深く掘り下げていきます。
肩こりや更年期の症状に悩んでいる方、その原因や対処法を探している方は、ぜひこの記事を読んで、具体的な改善策を見つけてみてください。きっと、あなたに合った解決策が見つかるはずです。
1. 肩こりと更年期障害の関係性
更年期になると、肩こりがひどくなった、あるいは新しく肩こりが始まったという女性が多くいらっしゃいます。実は、肩こりと更年期障害には密接な関係があるのです。更年期は、閉経をはさんだ前後10年間ほどの期間を指し、この時期には卵巣機能が低下することで女性ホルモンの分泌が不安定になります。このホルモンバランスの乱れが、自律神経のバランスを崩し、様々な不調を引き起こすのです。肩こりもその一つです。
1.1 更年期になるとなぜ肩こりが起こりやすいのか
更年期に肩こりが起こりやすいのは、主に女性ホルモンのエストロゲンの減少が関わっています。エストロゲンには、血管を拡張し血行を良くする作用、自律神経のバランスを整える作用、筋肉の緊張を和らげる作用などがあります。更年期でエストロゲンが減少すると、これらの作用が弱まり、結果として血行不良や筋肉の緊張、自律神経の乱れが生じ、肩こりにつながりやすくなるのです。
また、エストロゲンの減少は、コラーゲンの生成にも影響を与えます。コラーゲンは、骨や筋肉、血管などを支えるタンパク質の一種で、肩や首の柔軟性を保つためにも重要な役割を果たしています。エストロゲンが減少することでコラーゲンの生成も減少すると、肩や首の筋肉や関節の柔軟性が低下し、肩こりが悪化しやすくなります。
| エストロゲンの減少による影響 | 肩こりへの影響 |
| 血行不良 | 筋肉や組織への酸素供給不足、老廃物の蓄積 |
| 自律神経の乱れ | 交感神経の優位による筋肉の緊張 |
| コラーゲンの減少 | 肩や首の柔軟性低下 |
| 筋肉の緊張緩和作用の低下 | 肩や首の筋肉が硬くなりやすい |
1.2 肩こり以外の更年期によくある症状
更年期障害の症状は実に多様で、個人差も大きいです。肩こりの他に、代表的な症状として、ホットフラッシュ、のぼせ、発汗、冷え、めまい、動悸、息切れ、不眠、イライラ、不安感、抑うつ、倦怠感、頭痛、腰痛、関節痛、性交痛、頻尿、皮膚の乾燥、などがあります。これらの症状は単独で現れることもあれば、複数同時に現れることもあります。
更年期障害は、これらの症状が日常生活に支障をきたすほど重くなる場合があり、適切な対処が必要となります。もし、更年期と思われる症状でお困りの際は、一人で悩まずに、専門家に相談することをお勧めします。
2. 肩こりの原因
肩こりは、現代社会において非常に多くの人が抱える悩みのひとつです。その原因は多岐にわたり、複雑に絡み合っていることが多く、根本的な解決には原因の特定が重要となります。ここでは、肩こりの主な原因を詳しく解説していきます。
2.1 筋肉の緊張
長時間同じ姿勢を続けたり、過度な運動をしたりすると、筋肉が緊張し、硬くなります。特に、デスクワークやスマートフォンの長時間使用は、首や肩周りの筋肉に負担をかけ、肩こりの大きな原因となります。筋肉の緊張が続くと、血行不良を引き起こし、さらに肩こりを悪化させることもあります。
2.1.1 デスクワーク
パソコン作業や書類仕事など、デスクワーク中心の生活は、肩こりの大きな要因となります。長時間同じ姿勢を続けることで、首や肩、背中の筋肉が緊張し、血行が悪くなります。また、キーボードやマウス操作による腕や手首の疲労も、肩こりに繋がることがあります。
2.1.2 スマートフォンの長時間使用
スマートフォンを長時間使用すると、うつむいた姿勢が続くため、首や肩に大きな負担がかかります。この姿勢は「ストレートネック」と呼ばれる状態を引き起こし、肩こりだけでなく、頭痛や吐き気を伴う場合もあります。
2.1.3 運動不足
運動不足は、筋肉の柔軟性を低下させ、血行不良を招きます。適度な運動は、筋肉を強化し、血行を促進するため、肩こりの予防に効果的です。
2.2 血行不良
血行不良は、筋肉や組織に十分な酸素や栄養が供給されなくなるため、老廃物が蓄積し、肩こりを引き起こします。冷え性や運動不足、ストレスなども血行不良を悪化させる要因となります。
2.2.1 冷え性
冷え性の方は、末梢血管が収縮しやすく、血行が悪くなりやすい傾向があります。特に、冬場は肩こりが悪化しやすいため、保温対策が重要です。
2.2.2 運動不足
運動不足は、筋肉のポンプ作用を低下させ、血行不良を招きます。適度な運動は、血行を促進し、肩こりの予防・改善に繋がります。
2.3 姿勢の悪さ
猫背や頭が前に出ている姿勢は、首や肩周りの筋肉に負担をかけ、肩こりを引き起こしやすくなります。正しい姿勢を意識することで、肩こりの予防・改善に繋がります。
2.3.1 猫背
猫背は、背中が丸まり、頭が前に出る姿勢です。この姿勢は、肩甲骨周りの筋肉が引っ張られ、肩こりを引き起こします。また、呼吸が浅くなり、酸素供給が不足することも、肩こりの原因となります。
2.3.2 ストレートネック
ストレートネックは、本来緩やかなカーブを描いている頸椎がまっすぐになっている状態です。この状態は、首や肩への負担が増大し、肩こりや頭痛の原因となります。スマートフォンの長時間使用やデスクワークなどで起こりやすい姿勢です。
2.4 ストレス
ストレスは、自律神経のバランスを崩し、筋肉を緊張させ、血行不良を引き起こすため、肩こりの原因となります。ストレスを解消するためのリラックス方法を見つけることが重要です。
| ストレスの種類 | 影響 |
| 精神的ストレス | 不安や緊張、イライラなど、精神的なストレスは、自律神経のバランスを崩し、筋肉の緊張を高めます。 |
| 身体的ストレス | 過労や睡眠不足、栄養不足など、身体的なストレスも、筋肉の疲労や血行不良を引き起こし、肩こりに繋がります。 |
| 環境的ストレス | 騒音や寒さ、人間関係など、周囲の環境によるストレスも、肩こりを悪化させる要因となります。 |
2.5 更年期障害によるホルモンバランスの乱れ
更年期になると、女性ホルモンであるエストロゲンの分泌量が減少します。エストロゲンには、自律神経の調整や血行促進、筋肉の緊張を緩和する作用があるため、その減少は、自律神経の乱れや血行不良、筋肉の緊張を引き起こし、肩こりを悪化させる一因となります。
更年期障害による肩こりは、他の原因による肩こりと比べて、症状が重く、慢性化しやすい傾向があります。また、頭痛や吐き気、めまいなどの症状を伴う場合もあります。更年期障害が疑われる場合は、医療機関への相談も検討しましょう。
3. 更年期障害の原因
更年期障害は、閉経を挟んだ前後10年間ほどの更年期に起こる様々な不調の総称です。加齢とともに卵巣機能が低下し、女性ホルモンの分泌量が急激に減少することが主な原因ですが、それ以外にも様々な要因が複雑に絡み合って発症すると考えられています。
3.1 女性ホルモンの減少
更年期障害の最も大きな原因は、女性ホルモン(エストロゲン)の減少です。エストロゲンは、女性の心身の状態を安定させるために重要な役割を担っています。自律神経の働きや血管の収縮・拡張、体温調節、コラーゲンの生成など、多岐にわたる機能に関与しています。そのため、エストロゲンの分泌量が減少すると、これらの機能がうまく働かなくなり、様々な不調が現れます。
3.1.1 エストロゲンの急激な減少による影響
• 自律神経の乱れ
• 血管運動神経の失調によるほてりやのぼせ
• 精神的な不安定
• 骨密度の低下
3.2 自律神経の乱れ
自律神経は、呼吸や消化、体温調節など、生命維持に欠かせない機能を無意識のうちにコントロールしています。自律神経には、活動時に優位になる交感神経と、休息時に優位になる副交感神経の2種類があり、これらがバランスよく働くことで健康な状態が保たれます。しかし、更年期にはエストロゲンの減少によってこのバランスが崩れやすくなり、自律神経の乱れが生じます。その結果、めまい、動悸、息切れ、発汗、冷え、便秘、下痢など、様々な症状が現れます。
3.2.1 自律神経の乱れやすい更年期世代の特徴
• ホルモンバランスの変動
• ストレスへの感受性の変化
• 生活環境の変化(子どもの独立、親の介護など)
3.3 加齢による身体の変化
更年期は、一般的に40代後半から50代にかけて訪れます。この時期は、加齢に伴う身体の変化も顕著になる時期です。血管の老化や骨密度の低下などが進行し、更年期障害の症状を悪化させる要因となることがあります。また、身体の機能低下によって疲れやすくなったり、体力が落ちたりすることも、更年期障害の症状の一つとして現れることがあります。
| 身体の変化 | 更年期障害への影響 |
| 血管の弾力性の低下 | 血圧の変動、動悸、めまい |
| 骨密度の減少 | 骨粗鬆症のリスク増加 |
| 基礎代謝の低下 | 体重増加、疲労感 |
3.4 ストレスや生活習慣
更年期世代は、仕事や家庭、子育て、介護など、様々なストレスにさらされやすい時期でもあります。過剰なストレスは自律神経のバランスを崩し、更年期障害の症状を悪化させる可能性があります。また、睡眠不足、栄養バランスの偏った食事、運動不足などの生活習慣の乱れも、更年期障害の症状を助長する要因となります。バランスの取れた食生活、適度な運動、質の高い睡眠を心がけることが大切です。
3.4.1 生活習慣改善のポイント
• 規則正しい生活リズムを維持する
• 栄養バランスの良い食事を摂る
• 適度な運動を習慣づける
• リラックスできる時間を作る
• 趣味や好きなことに没頭する
4. 肩こりの対処法
肩こりは、放置すると慢性化し、日常生活にも支障をきたすことがあります。つらい肩こりを解消するために、様々な対処法を試してみましょう。自分に合った方法を見つけることが大切です。
4.1 ストレッチ
肩こりの原因となる筋肉の緊張を和らげるためには、ストレッチが効果的です。肩甲骨を意識的に動かすことで、周辺の筋肉がほぐれて血行が促進されます。
4.1.1 肩甲骨ストレッチ
1. 両手を前に伸ばし、手のひらを合わせます。
2. 息を吸いながら、両腕を頭上に持ち上げます。
3. 息を吐きながら、両肘を曲げ、肩甲骨を寄せるようにします。
4. この動作を数回繰り返します。
4.1.2 首のストレッチ
1. 頭をゆっくりと右に傾け、右手を左耳の上に添えます。
2. 優しく頭を右側に倒し、首の左側を伸ばします。
3. 反対側も同様に行います。
4.2 マッサージ
マッサージは、肩こりの原因となる血行不良を改善し、筋肉の緊張を和らげる効果があります。入浴後など体が温まっている時に行うとより効果的です。ただし、強い痛みを感じる場合は無理に行わないようにしましょう。
4.2.1 セルフマッサージ
1. 首の付け根から肩にかけて、指で優しく円を描くようにマッサージします。
2. 肩甲骨の内側を親指で押しながら、上下に動かします。
4.3 温熱療法
温熱療法は、血行を促進し、筋肉の緊張を和らげる効果があります。蒸しタオルや温湿布、お風呂などで体を温めることで、肩こりの緩和が期待できます。低温やけどには注意しましょう。
| 方法 | 効果 | 注意点 |
| 蒸しタオル | 手軽に温められる | 冷めやすい |
| 温湿布 | 持続的に温められる | 低温やけどに注意 |
| お風呂 | 全身を温められる | 長湯は避ける |
4.4 運動療法
適度な運動は、血行を促進し、筋肉を強化する効果があります。ウォーキングや水泳など、全身を使う運動がおすすめです。激しい運動は逆効果になる場合があるので、自分の体力に合った運動を選びましょう。
4.5 姿勢の改善
猫背などの悪い姿勢は、肩こりの大きな原因となります。正しい姿勢を意識することで、肩への負担を軽減し、肩こりを予防することができます。デスクワークが多い方は、こまめに休憩を取り、軽いストレッチを行うようにしましょう。
これらの対処法を組み合わせて行うことで、より効果的に肩こりを改善することができます。また、これらの方法を試しても改善が見られない場合は、専門家への相談も検討しましょう。
5. 更年期障害の対処法
更年期障害の症状は多岐にわたり、その対処法も様々です。ご自身の症状や生活スタイルに合った方法を選び、辛い時期を乗り越えましょう。
5.1 ホルモン補充療法(HRT)
ホルモン補充療法(HRT)は、減少した女性ホルモンを補う治療法です。更年期障害の様々な症状を緩和する効果が期待できますが、副作用やリスクも存在するため、医師との相談が不可欠です。治療を受ける場合は、メリットとデメリットをしっかり理解した上で判断しましょう。
5.2 漢方薬
漢方薬は、自然の生薬を組み合わせた治療法で、体全体のバランスを整えることで更年期障害の症状を改善します。西洋医学とは異なるアプローチで、体質に合わせた漢方薬を選ぶことが大切です。 専門家による適切な診断と処方が必要となります。
5.3 生活習慣の改善
5.3.1 規則正しい生活
睡眠不足や不規則な生活は、自律神経の乱れを招き、更年期障害の症状を悪化させる可能性があります。毎日同じ時間に寝起きし、十分な睡眠時間を確保するよう心がけましょう。
5.3.2 バランスの良い食事
栄養バランスの取れた食事は、健康維持に不可欠です。特に、更年期には女性ホルモンの減少に伴い骨粗鬆症のリスクが高まるため、カルシウムやビタミンDを積極的に摂取しましょう。大豆製品に含まれるイソフラボンは、女性ホルモンと似た働きをするため、積極的に摂り入れると良いでしょう。
| 栄養素 | 多く含まれる食品 |
| カルシウム | 牛乳、ヨーグルト、チーズ、小魚、緑黄色野菜 |
| ビタミンD | 鮭、さんま、きのこ類 |
| イソフラボン | 豆腐、納豆、味噌、豆乳 |
5.3.3 適度な運動
適度な運動は、血行促進やストレス軽減に効果的です。ウォーキングやヨガなど、無理なく続けられる運動を選びましょう。運動習慣のない方は、軽い運動から始め、徐々に強度や時間を増やしていくと良いでしょう。
5.4 食事療法
更年期障害の症状緩和には、バランスの良い食事が重要です。特に、カルシウム、ビタミンD、イソフラボン、マグネシウムなどを積極的に摂取するように心がけましょう。
| 栄養素 | 期待される効果 | 多く含まれる食品 |
| カルシウム | 骨粗鬆症予防 | 牛乳、ヨーグルト、チーズ、小魚 |
| ビタミンD | カルシウムの吸収促進 | 鮭、さんま、きのこ類 |
| イソフラボン | 女性ホルモン様作用 | 豆腐、納豆、味噌 |
| マグネシウム | 精神安定、骨形成 | アーモンド、ひじき、ほうれん草 |
5.5 ストレスマネジメント
5.5.1 リラックスできる時間を作る
ストレスは更年期障害の症状を悪化させる要因の一つです。趣味や好きなことをする時間、ゆったりと入浴する時間など、リラックスできる時間を作ることは、心身の健康維持に役立ちます。
5.5.2 呼吸法や瞑想
深い呼吸を意識したり、瞑想を行うことで、自律神経のバランスを整え、心身をリラックスさせることができます。呼吸法や瞑想は、場所を選ばず手軽に行えるため、日常生活に取り入れやすい方法です。
5.5.3 相談できる相手を見つける
家族や友人、専門家など、悩みや不安を相談できる相手がいることは、心の支えになります。一人で抱え込まずに、周りの人に助けを求めることも大切です。
6. 鍼灸が肩こり・更年期障害に効果的な理由
肩こりや更年期障害でお悩みの方にとって、鍼灸は心強い味方となる可能性を秘めています。西洋医学とは異なるアプローチで、身体本来の力を引き出し、つらい症状を和らげる効果が期待できるからです。鍼灸がこれらの症状にどのように作用するのか、詳しく見ていきましょう。
6.1 自律神経の調整作用
更年期障害の大きな原因の一つに、自律神経の乱れがあります。自律神経は、体温調節や消化吸収、ホルモン分泌など、生命維持に欠かせない機能をコントロールしています。この自律神経のバランスが崩れると、様々な不調が現れます。鍼灸治療は、自律神経のバランスを整える効果があるとされています。鍼やお灸の刺激が自律神経に働きかけ、乱れた機能を正常化へと導くのです。更年期障害に伴うほてりやのぼせ、発汗、冷え、不眠などの症状緩和にも繋がると考えられています。
6.2 血行促進効果
肩こりの主な原因は、筋肉の緊張や血行不良です。長時間のデスクワークや姿勢の悪さ、冷えなどによって血行が悪くなると、筋肉に十分な酸素や栄養が供給されず、老廃物が蓄積されます。これが肩こりの原因となるのです。鍼灸治療は、血行を促進する効果も期待できます。鍼やお灸の刺激が血管を拡張し、血流を改善することで、筋肉への酸素供給を増やし、老廃物の排出を促します。肩こりの原因となる筋肉の緊張を和らげ、こり固まった肩を楽にする効果が期待できます。
6.3 筋肉の緩和作用
肩こりは、筋肉の緊張が大きな原因です。鍼灸治療は、筋肉の緊張を緩和する効果も期待できます。鍼を筋肉に刺入することで、筋肉の過剰な緊張を和らげ、柔軟性を取り戻す効果が期待できるのです。また、トリガーポイントと呼ばれる、こりの原因となる特定の部位に鍼を刺すことで、より効果的に肩こりの症状を改善できると考えられています。肩こりの原因となる筋肉の緊張を直接的に緩和することで、つらい肩こりを根本から改善へと導きます。
6.4 ホルモンバランスの調整作用
更年期障害は、女性ホルモンの減少によって引き起こされます。鍼灸治療は、ホルモンバランスの調整に効果があるとされています。鍼やお灸の刺激が脳下垂体に働きかけ、ホルモン分泌を促すことで、更年期障害の症状緩和に繋がると考えられています。更年期障害による様々な不調を、身体の内側から整えることで根本的な改善を目指します。
6.5 更年期障害による肩こりの鍼灸治療
更年期障害による肩こりは、ホルモンバランスの乱れや自律神経の乱れが原因で起こることが多く、一般的な肩こりとは異なるアプローチが必要となる場合があります。鍼灸治療では、これらの原因に直接アプローチすることで、更年期障害による肩こりを効果的に改善できると考えられています。
| 症状 | 鍼灸治療のポイント | 期待される効果 |
| 肩こり | 肩や首周りの筋肉に鍼を刺し、血行を促進、筋肉の緊張を緩和 | 肩こりの緩和、肩周りの可動域の改善 |
| ほてり、のぼせ | 自律神経を整えるツボに鍼やお灸を施す | ほてりやのぼせの軽減、発汗の抑制 |
| 冷え | 下肢の血行を促進するツボに鍼やお灸を施す | 冷えの改善、体温調節機能の正常化 |
| 不眠 | リラックス効果を高めるツボに鍼やお灸を施す | 睡眠の質の向上、不眠の解消 |
| イライラ、不安感 | 精神を安定させるツボに鍼やお灸を施す | 精神的な安定、イライラや不安感の軽減 |
更年期障害による肩こりは、他の症状と合わせて現れることが多いため、身体全体のバランスを整えることが重要です。鍼灸治療は、局所的な治療だけでなく、全身の調整を行うことで、更年期障害による様々な症状を総合的に改善へと導きます。
7. まとめ
肩こりは、筋肉の緊張や血行不良、姿勢の悪さ、ストレスなど様々な原因で起こりますが、更年期障害によるホルモンバランスの乱れも大きな要因となります。更年期障害は、女性ホルモンの減少に伴い、自律神経の乱れや身体の変化、またストレスや生活習慣の影響を受け発症します。肩こりも更年期障害も、放置すると日常生活に支障をきたす可能性があります。つらい症状を改善するためには、それぞれの原因に合わせた適切な対処法を選択することが重要です。
肩こりの対処法としては、ストレッチやマッサージ、温熱療法、運動療法、姿勢の改善などが挙げられます。更年期障害には、ホルモン補充療法、漢方薬、生活習慣の改善、食事療法、ストレスマネジメントなどが有効です。そして、肩こりと更年期障害の両方に効果的なのが鍼灸治療です。鍼灸は、自律神経やホルモンバランス、血行を調整し、筋肉の緊張を緩和する効果が期待できます。更年期障害による肩こりに悩んでいる方は、鍼灸治療を試してみる価値があるでしょう。
つらい肩こりや更年期障害の症状でお悩みの方は、当院へご相談ください。
あなたへのオススメ記事
- 健康について,治療について肩こり高血圧は危険信号?原因と鍼灸による対処法を徹底解説!
- 健康について,日常について秋バテ防止!
- 健康について肩こり解消に筋トレは効果あり?鍼灸との併用で最強の肩こり対策!
診療時間
| 受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00~12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー |
| 15:00~19:30 | ● | ● | ー | ● | ● | ー | ー |
■ 休診日 日曜・祝日・水曜午後・土曜午後

〒537-0002
大阪府大阪市東成区深江南1丁目13−4
シャトーブラン BI HORIE 1F
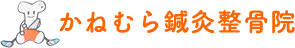
 お問い合わせ
お問い合わせ





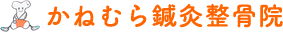
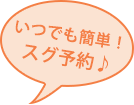
 LINEでお問い合わせ
LINEでお問い合わせ

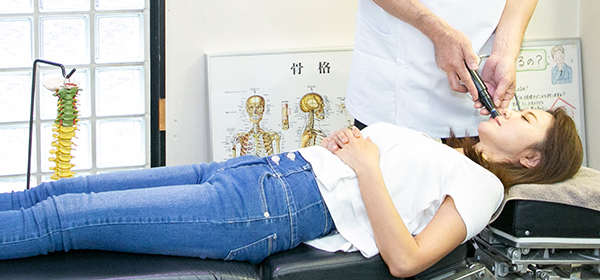


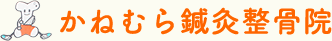
 ご予約・お問い合わせはこちら
ご予約・お問い合わせはこちら