ブログ

ブログ
腰痛とすべり症の本当の原因!鍼灸で改善できるってホント?徹底解説
2025/05/09
慢性的な腰痛に悩まされ、もしかしてすべり症かも?と不安を抱えている方はいませんか? このページでは、腰痛とすべり症の関係性について詳しく解説し、鍼灸治療の効果と限界、そして日常生活での予防策まで網羅的にご紹介します。
すべり症とは何か、その種類や原因、すべり症以外の腰痛の原因についても分かりやすく説明しますので、ご自身の症状の理解に役立てていただけます。さらに、鍼灸がすべり症による腰痛にどのように作用するのか、そのメカニズムや治療頻度、期間の目安、そして他の治療法についてもご紹介します。
この記事を読むことで、すべり症による腰痛の不安を解消し、適切な治療法や日常生活でのケア方法を見つけるためのヒントを得られるでしょう。辛い腰痛を根本から改善し、快適な毎日を送るための一助となれば幸いです。
1. 腰痛とすべり症の関係
腰痛は、現代人にとって非常に身近な症状です。その原因は様々ですが、中でも「すべり症」が腰痛を引き起こすケースは少なくありません。この章では、腰痛とすべり症の関係性について詳しく解説していきます。
1.1 そもそもすべり症とは?
すべり症とは、背骨を構成する椎骨が、本来あるべき位置からずれてしまう状態を指します。上にある椎骨が、下にある椎骨に対して前方にずれることが一般的です。このずれによって、周囲の神経や組織が圧迫され、腰痛をはじめとする様々な症状が現れます。加齢や激しいスポーツ、外傷などが原因となる場合もあります。
1.2 すべり症が腰痛を引き起こすメカニズム
すべり症によって腰痛が発生するメカニズムは主に以下の通りです。
- 神経根の圧迫:ずれた椎骨が神経根を圧迫することで、腰だけでなく、臀部や太もも、足先まで響くような痛みやしびれを引き起こします。この痛みは、姿勢の変化や動作によって悪化することがあります。
- 椎間関節への負担増加:椎骨のずれは、椎骨同士をつなぐ椎間関節への負担を増大させます。これにより、関節の炎症や変形が生じ、腰痛の原因となります。
- 周囲の筋肉の緊張:ずれた椎骨を支えようと、周囲の筋肉が過剰に緊張します。この筋肉の緊張が、腰痛や背中のこわばりを引き起こす要因となります。長期間続くと、筋肉の疲労や血行不良も併発し、慢性的な腰痛につながる可能性があります。
- 馬尾神経症候群:重度のすべり症の場合、馬尾神経と呼ばれる神経の束が圧迫されることがあります。これは、排尿・排便障害や下肢の麻痺などの深刻な症状を引き起こすため、注意が必要です。このような症状が現れた場合は、すぐに専門機関への受診が必要です。
| すべり症の程度 | 症状 |
| 軽度 | 腰痛、軽いしびれ、違和感 |
| 中等度 | 強い腰痛、下肢への放散痛、しびれ |
| 重度 | 激しい腰痛、下肢の麻痺、排尿・排便障害 |
すべり症は、程度によって症状が大きく異なります。軽度のすべり症では、腰の痛みや軽いしびれを感じる程度ですが、重症化すると下肢の麻痺や排尿・排便障害などの深刻な症状が現れることもあります。そのため、早期発見と適切な対処が重要です。
2. 腰痛の原因となるすべり症の種類
すべり症にはいくつかの種類があり、それぞれ原因や症状が異なります。ご自身の症状を理解するためにも、すべり症の種類について知っておきましょう。
2.1 変性すべり症
変性すべり症は、加齢に伴う椎間板や椎体の変性、靭帯の緩みなどが原因で起こる、最も一般的なすべり症です。特に女性に多く見られます。椎間板の弾力性が失われ、椎体の骨棘形成などが進むことで、上側の椎体が前方にずれてしまうのです。初期には自覚症状がない場合も多いですが、徐々に腰痛や下肢痛、しびれなどの症状が現れます。長時間の立位や歩行で症状が悪化し、安静にすることで軽減するのが特徴です。
2.2 分離すべり症
分離すべり症は、椎弓の一部である峡部と呼ばれる部分が骨折することで、椎体が前方にずれるすべり症です。成長期におけるスポーツや外傷などが原因で発症することが多く、若年層に多く見られます。軽度のずれでは無症状のこともありますが、進行すると腰痛や下肢痛、しびれなどの症状が現れます。腰を反らす動作で痛みが強くなるのが特徴です。
2.3 峡部すべり症
峡部すべり症は、先天的に峡部が形成不全である場合や、疲労骨折によって峡部が分離した結果、上側の椎体が前方にずれるすべり症です。分離すべり症と同様に、若年層に多く発症します。腰痛や下肢痛、しびれなどの症状が現れ、腰を反らすと痛みが強くなります。分離すべり症との鑑別が重要です。
2.4 外傷性すべり症
外傷性すべり症は、交通事故や転倒など、強い外力によって椎体が骨折し、ずれることで起こるすべり症です。骨折の程度や部位によって症状は様々ですが、激しい腰痛や神経症状が現れることがあります。緊急性の高い場合もあり、迅速な診断と治療が必要です。
2.5 病的すべり症
病的すべり症は、骨腫瘍や感染症など、他の病気が原因で椎体が破壊され、ずれることで起こるすべり症です。基礎疾患の治療が重要となります。症状は基礎疾患の種類や進行度によって様々です。
| すべり症の種類 | 主な原因 | 好発年齢 | 特徴 |
| 変性すべり症 | 加齢による椎間板・椎体の変性、靭帯の緩み | 中高年 | 長時間の立位・歩行で悪化、安静で軽減 |
| 分離すべり症 | 峡部の骨折(スポーツ、外傷など) | 若年層 | 腰を反らすと痛みが増強 |
| 峡部すべり症 | 峡部の形成不全、疲労骨折 | 若年層 | 腰を反らすと痛みが増強 |
| 外傷性すべり症 | 強い外力による椎体骨折 | 様々 | 激しい腰痛、神経症状 |
| 病的すべり症 | 骨腫瘍、感染症など | 様々 | 基礎疾患による |
これらのすべり症は、症状や原因によって適切な治療法が異なります。自己判断せずに、専門家に相談することが大切です。
3. すべり症以外の腰痛の原因
腰痛は、すべり症以外にも様々な原因で引き起こされます。それぞれの特徴を理解し、適切な対処をすることが重要です。
3.1 椎間板ヘルニア
椎間板ヘルニアは、背骨の間にある椎間板という組織の一部が飛び出し、神経を圧迫することで腰痛や下肢の痛みやしびれを引き起こす疾患です。重いものを持ち上げた時や、くしゃみをした時など、急激な動作がきっかけで発症することがあります。また、長時間のデスクワークや運転など、同じ姿勢を続けることも原因の一つと考えられています。特に腰椎に多く発生し、下肢の痛みやしびれ、感覚障害などを伴う坐骨神経痛を引き起こすこともあります。
3.2 脊柱管狭窄症
脊柱管狭窄症は、背骨の中を通る脊柱管が狭くなり、神経が圧迫されることで腰痛や下肢の痛みやしびれを引き起こす疾患です。加齢による骨や靭帯の変性が主な原因で、50歳以上の方に多く発症します。特徴的な症状として、間歇性跛行と呼ばれる、歩行すると下肢の痛みやしびれが増悪し、少し休むと軽減するという症状が見られます。
3.3 筋筋膜性腰痛
筋筋膜性腰痛は、腰や骨盤周囲の筋肉や筋膜の緊張や炎症によって引き起こされる腰痛です。長時間同じ姿勢での作業や、過度な運動、精神的なストレスなどが原因となることがあります。腰や臀部に痛みやこり、違和感を感じ、特定の動作で痛みが悪化することがあります。トリガーポイントと呼ばれる、押すと痛みを感じる特定の部位が存在することも特徴です。
3.4 仙腸関節障害
仙腸関節障害は、骨盤を構成する仙骨と腸骨の間にある仙腸関節に炎症や機能障害が生じることで腰痛や臀部の痛みを引き起こす疾患です。妊娠・出産、転倒、交通事故などの外傷、長時間の立ち仕事や、脚長差などが原因となることがあります。腰や臀部、脚の付け根に痛みを感じ、長時間同じ姿勢を続けたり、体をひねったりすると痛みが悪化することがあります。
| 疾患名 | 主な原因 | 主な症状 |
| 椎間板ヘルニア | 重いものを持ち上げる、くしゃみ、長時間のデスクワークなど | 腰痛、下肢の痛みやしびれ、坐骨神経痛 |
| 脊柱管狭窄症 | 加齢による骨や靭帯の変性 | 腰痛、下肢の痛みやしびれ、間歇性跛行 |
| 筋筋膜性腰痛 | 長時間同じ姿勢での作業、過度な運動、精神的なストレス | 腰や臀部の痛みやこり、特定の動作で痛みが悪化 |
| 仙腸関節障害 | 妊娠・出産、転倒、交通事故、長時間の立ち仕事、脚長差 | 腰や臀部、脚の付け根の痛み、姿勢や動作による痛みの悪化 |
これらの他にも、内臓疾患や腫瘍などが原因で腰痛が生じる場合もあります。腰痛が長引く場合や、強い痛みがある場合は、自己判断せずに専門家に相談することが大切です。
4. 鍼灸ですべり症による腰痛は本当に改善するのか?
すべり症による腰痛に鍼灸が効果的かどうかは、多くの患者さんが抱える疑問です。結論から言うと、鍼灸はすべり症に伴う腰痛を改善する可能性を秘めていますが、その効果は症状の程度や個人差によって異なり、すべり症自体を治すものではありません。鍼灸治療はあくまで対症療法であり、根本的な解決には至らないケースもあることを理解しておく必要があります。
4.1 鍼灸の腰痛への作用機序
鍼灸は、身体に鍼を刺したり灸で温めたりすることで、様々な生理作用を誘発し、腰痛の緩和に繋がると考えられています。主な作用機序は以下の通りです。
- 鎮痛作用:鍼灸刺激は、脳内でエンドルフィンなどの鎮痛物質の分泌を促進し、痛みを軽減する効果が期待できます。
- 血行促進作用:鍼灸刺激によって血行が促進され、筋肉や組織への酸素供給が向上し、老廃物の排出が促されます。これにより、筋肉の緊張が緩和され、痛みが軽減されます。
- 筋緊張緩和作用:鍼灸刺激は、筋肉の緊張を緩和する効果があります。すべり症に伴う腰痛は、周囲の筋肉の緊張が原因となる場合も多く、鍼灸はこの緊張を和らげることで痛みを軽減します。
- 自律神経調整作用:鍼灸刺激は自律神経のバランスを整える効果も期待できます。自律神経の乱れは、痛みを増幅させる要因となるため、自律神経を整えることで痛みの悪循環を断ち切ることが期待できます。
4.2 すべり症への鍼灸の効果と限界
鍼灸は、すべり症に伴う腰痛、特に筋肉の緊張や炎症による痛みに効果を発揮する可能性があります。しかし、骨の変形や神経の圧迫といったすべり症の根本原因を解消するものではありません。
また、効果の感じ方には個人差があり、すべての人に効果があるとは限りません。重度のすべり症や神経症状を伴う場合は、鍼灸だけでは十分な効果が得られない場合もあります。そのような場合は、他の治療法との併用が必要となるでしょう。
4.2.1 治療頻度と期間
鍼灸治療の頻度や期間は、症状の程度や個々の状態によって異なります。一般的には、週に1~2回程度の治療を数週間~数ヶ月継続することで効果が期待できます。ただし、治療効果が現れるまでの期間にも個人差があります。治療開始後すぐに効果を実感できる場合もあれば、数回治療を受けて徐々に効果が現れる場合もあります。
| 症状の程度 | 治療頻度 | 治療期間 |
| 軽度 | 週1回 | 数週間~数ヶ月 |
| 中等度 | 週1~2回 | 数ヶ月 |
| 重度 | 週2回 | 数ヶ月~長期 |
治療期間や頻度については、施術者と相談しながら最適なプランを立てていくことが重要です。また、治療効果がなかなか現れない場合も、焦らずに施術者と相談し、治療方針の見直しなどを検討しましょう。
5. 腰痛・すべり症の鍼灸以外の治療法
鍼灸以外にも、腰痛やすべり症に対して様々な治療法が存在します。症状の程度や種類、個々の状態に合わせて適切な治療法を選択することが重要です。大きく分けて保存療法と手術療法があります。
5.1 保存療法
保存療法は、手術を行わずに症状の改善を目指す治療法です。比較的症状が軽い場合や、手術のリスクが高い場合に選択されます。主な保存療法には、薬物療法、理学療法、装具療法などがあります。
5.1.1 薬物療法
痛みや炎症を抑える薬を用いて、症状の緩和を図ります。主な薬としては、非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)、アセトアミノフェン、筋弛緩薬などがあります。痛みが強い場合には、神経ブロック注射を行うこともあります。
5.1.2 理学療法
理学療法士による指導のもと、ストレッチ、筋力トレーニング、温熱療法、電気刺激療法などを行います。腰周りの筋肉を強化し、柔軟性を高めることで、腰痛の改善や再発予防を目指します。牽引療法も、すべり症による神経の圧迫を軽減する効果が期待できます。
5.1.3 装具療法
コルセットなどの装具を装着することで、腰椎を安定させ、痛みを軽減します。すべり症の進行を抑える効果も期待できます。症状や生活スタイルに合わせて、適切な装具を選択します。
5.2 手術療法
保存療法で効果が得られない場合や、神経症状が進行している場合などには、手術療法が検討されます。主な手術方法には、除圧術、固定術などがあります。
| 手術方法 | 概要 | 対象となる症状 |
| 除圧術 | 神経を圧迫している骨や組織を取り除き、神経の圧迫を解除する手術。 | 神経症状(しびれ、痛みなど)が強い場合 |
| 固定術 | 不安定な腰椎を金属で固定し、安定させる手術。 | すべり症の進行が著しい場合、腰椎の不安定性が強い場合 |
手術療法は、身体への負担が大きいため、慎重に検討する必要があります。術後のリハビリテーションも重要です。手術方法の選択は、患者の状態や症状、年齢などを考慮して決定されます。
6. 日常生活でできる腰痛・すべり症の予防と改善策
腰痛とすべり症の予防・改善には、日常生活における習慣の見直しが重要です。正しい姿勢や適度な運動、体重管理などを意識することで、症状の悪化を防ぎ、快適な生活を送るための土台を作ることができます。
6.1 正しい姿勢とストレッチ
不良姿勢は腰への負担を増大させ、すべり症の悪化や腰痛の誘発につながります。立っている時、座っている時、寝ている時、常に正しい姿勢を意識しましょう。具体的には、背筋を伸ばし、お腹に力を入れて骨盤を立てるようにします。猫背にならないよう注意し、顎を引いて目線をまっすぐに向けることも大切です。
ストレッチは、腰周りの筋肉の柔軟性を高め、血行を促進することで、腰痛の緩和や予防に効果的です。朝起きた時やお風呂上がりなど、毎日継続して行うことが大切です。腰を反らすストレッチ、腰をねじるストレッチ、前屈ストレッチなど、様々な種類のストレッチがあります。痛みのない範囲で無理なく行いましょう。下記にいくつか例を挙げます。
| ストレッチ名 | 方法 | 注意点 |
| 膝抱えストレッチ | 仰向けに寝て、両膝を胸に引き寄せる。 | 腰が反らないように注意する。 |
| 腰回しストレッチ | 両足を肩幅に開いて立ち、腰をゆっくりと回す。 | 無理に大きく回さない。 |
| ハムストリングスストレッチ | 椅子に座り、片足を伸ばし、つま先を上に上げる。 | 膝を曲げないようにする。 |
就寝時の姿勢にも注意が必要です。仰向けで寝る場合は、膝の下にクッションなどを置いて軽く曲げると、腰への負担を軽減できます。横向きで寝る場合は、両膝を軽く曲げ、抱き枕などを抱えると、体のバランスが安定しやすくなります。高すぎる枕は避け、首や肩への負担を軽減することも重要です。
6.2 適度な運動
適度な運動は、腰周りの筋肉を強化し、腰痛の予防・改善に繋がります。ウォーキングや水泳など、腰に負担の少ない運動を選び、無理なく継続することが大切です。激しい運動や急な動作は、逆に腰痛を悪化させる可能性があるので避けましょう。
腰痛がある場合は、痛みのない範囲で運動を行い、徐々に強度や時間を増やしていくようにしましょう。運動中に痛みを感じた場合は、すぐに中止し、安静するようにしてください。下記に腰痛に良いとされる運動の例を挙げます。
| 運動 | 効果 | 注意点 |
| ウォーキング | 腰への負担が少ない有酸素運動。 | 正しい姿勢で行う。 |
| 水泳 | 浮力により腰への負担が軽減される。 | クロールなど、腰を反らせる泳ぎは避ける。 |
| ヨガ | 体幹を鍛え、柔軟性を高める。 | 無理なポーズは避ける。 |
6.3 体重管理
過剰な体重は腰への負担を増大させ、腰痛やすべり症のリスクを高めます。バランスの取れた食事と適度な運動を心がけ、適体重を維持することが重要です。急激なダイエットは体に負担をかけるため、無理のない範囲で徐々に体重を減らしていくようにしましょう。
腹筋や背筋などの体幹を鍛えることは、腰への負担を軽減し、姿勢を安定させる効果があります。体幹トレーニングは、腰痛予防だけでなく、姿勢改善や基礎代謝向上にも効果的です。プランクやドローインなど、様々な種類の体幹トレーニングがあります。自分の体力や体調に合わせて、無理なく続けられる方法を選びましょう。
これらの日常生活における工夫を継続することで、腰痛とすべり症の予防・改善に繋がります。日々の生活の中で意識的に取り組むことで、健康な腰を維持し、快適な生活を送るための基盤を築きましょう。
7. まとめ
この記事では、腰痛とすべり症の関係、すべり症の種類、鍼灸の効果などについて解説しました。すべり症は、椎骨が前方にずれることで神経を圧迫し、腰痛を引き起こす病気です。加齢による変性すべり症が最も多く、その他分離すべり症、峡部すべり症、外傷性すべり症、病的すべり症などがあります。
すべり症以外にも、椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症、筋筋膜性腰痛、仙腸関節障害などが腰痛の原因となることがあります。
鍼灸は、腰痛の症状緩和に効果が期待できる治療法です。筋肉の緊張を緩和し、血行を促進することで痛みを軽減します。ただし、すべり症自体を治すことはできません。鍼灸治療は、他の保存療法と併用することでより効果的になります。
また、日常生活での姿勢や運動、体重管理も重要です。すべり症が進行している場合や、保存療法で効果がない場合は、手術療法が選択されることもあります。
腰痛は、原因によって適切な治療法が異なります。自己判断せず、医療機関を受診し、適切な診断と治療を受けるようにしましょう。何かお困りごとがありましたら当院へお問い合わせください。
あなたへのオススメ記事
- 健康について,治療について肩こり高血圧は危険信号?原因と鍼灸による対処法を徹底解説!
- 健康について,日常について秋バテ防止!
- 健康について肩こり解消に筋トレは効果あり?鍼灸との併用で最強の肩こり対策!
診療時間
| 受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00~12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー |
| 15:00~19:30 | ● | ● | ー | ● | ● | ー | ー |
■ 休診日 日曜・祝日・水曜午後・土曜午後

〒537-0002
大阪府大阪市東成区深江南1丁目13−4
シャトーブラン BI HORIE 1F
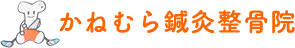
 お問い合わせ
お問い合わせ





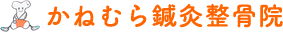
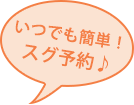
 LINEでお問い合わせ
LINEでお問い合わせ

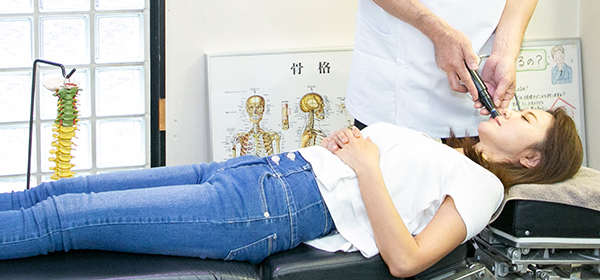


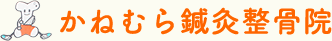
 ご予約・お問い合わせはこちら
ご予約・お問い合わせはこちら